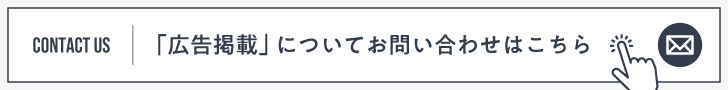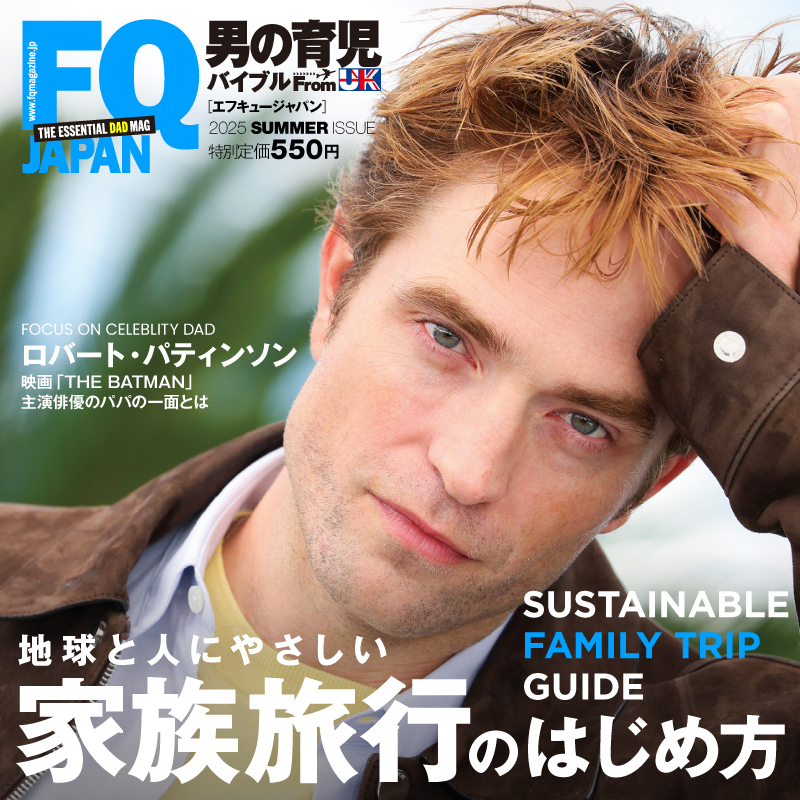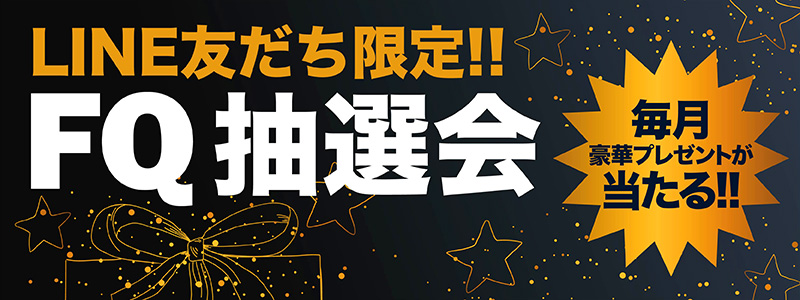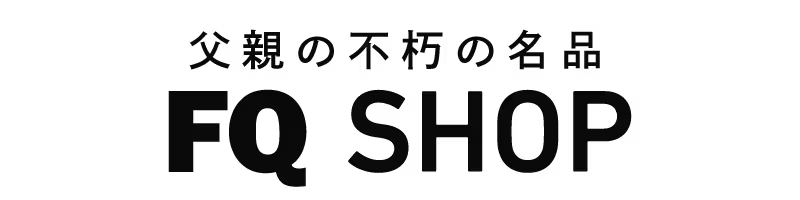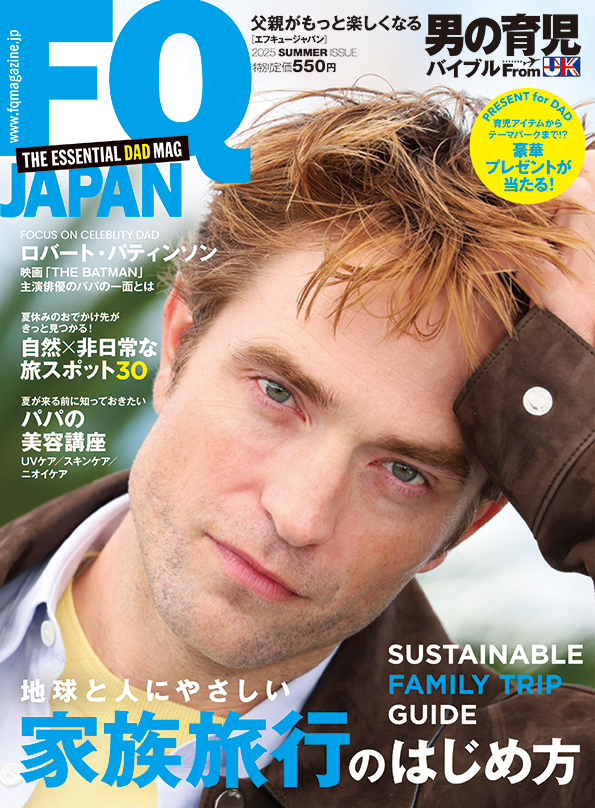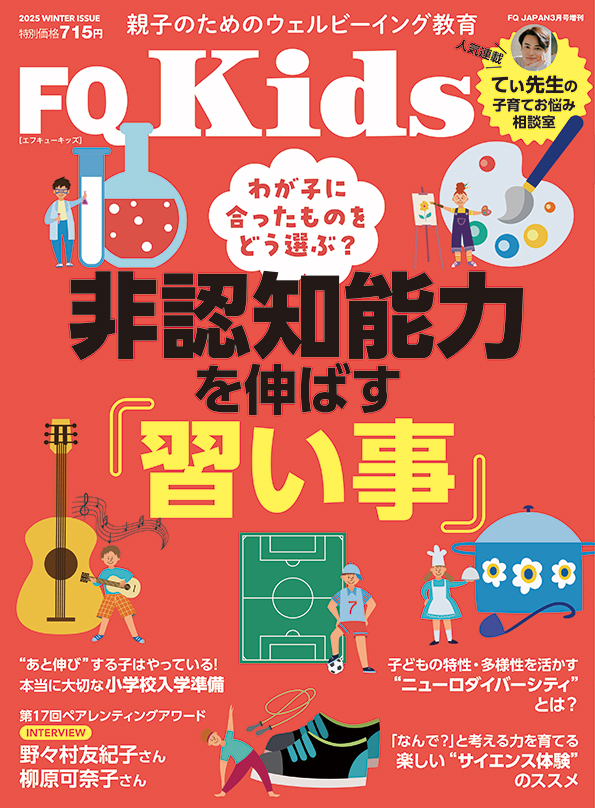宮台真司の”オトナ社会学” 子供に必要な「自然から見られている」という感受性とは?
2020/01/13

社会の外に開かれた感受性の典型が昔のアニミズム。「樹に精霊が宿る」という意味ではなく、「人間以外のものから見られる」「人間以外のものになりきる」という感覚だ。生物や無生物になりきれる感受性だけが、真に自然を持続させる。首都大学東京の宮台真司教授の「オトナ社会学」第7回目。
【第1話】イクメンはやっぱりファッションだった!? 3児のパパが語る(全4パート)
【第2話】損得で動く大人に育てるな!空洞家族にならないための「仲間」とは?
【第3話】多様性って何? 親が正しく学ぶべき「マイノリティ教育」の本質(前中後編)
【第4話】学校で子供が孤立しないための「周りに染まらない」生き方とは?
【第5話】子供に「ウソをつく」ことをどう教える? 重要なのは“何のためのウソか”
【第6話】宮台真司氏が勧める「モテ教育」とは? 子供を魅力的な人間に育てる方法
不安神経症の親が
子を抱え込んではダメ

子供の教育について考えると、このままでは日本の子供はダメになっていくでしょう。なぜなら親が感情的に劣化しているからです。
感情の劣化とは、刷り込まれた言葉のプログラムに閉じ込められた「言葉の自動機械」、法に閉じ込められた「法の奴隷」、ポジション取りに勤しむ「損得マシーン」になること。これらは神経症の徴候です。
神経症とは、死や孤独などの解消不可能な不安を、埋め合わせようとして、頓珍漢な行為を反復する精神病理の一種です。頓珍漢な行為とは、出かける前にガスの元栓を閉めたかどうか不安になって何度も確認するといった、不安の本体とは何の関係もない営みのこと。
親に抱え込まれないように、子供が幼少期から多様な大人と接する環境が大切です。今の大学生は、親と教員以外の大人と接した機会がなく、親の劣化が子供にうつります。
加えて、言葉の自動機械も、法の奴隷も、損得マシーンも、社会の中に閉じ込められた状態を意味します。だから、社会の外に開かれることも、重要な処方箋になります。
感受性を育てる
海外の教育方法

社会の外に開かれた感受性の典型が昔のアニミズム。「樹に精霊が宿る」という意味ではなく、「人間以外のものから見られる」「人間以外のものになりきる」という感覚です。
獣や爬虫類や虫だけでなく、花からも草からも樹木からも見られている。動植物だけでなく、山からも海からも雲からも見られている。見られているだけでなく、なりきれる。
そんな感受性を育てるのが、デンマークで小学校入学前の子供が森の中で自由に暮らす「森の幼稚園」や、ドイツの12年制一貫教育である「シュタイナー教育」の目的です。
クリエイティビティ向上のようなポジション取りは、単に結果の一つにすぎない。もっと重大なのは、社会に閉じ込められた親たちみたいな「クズ」の再生産をとめられること。
いいね!ボタンを欲しがる「意識高い系」みたいな、ポシション取りの「自然は大切」はどうでもいい。生物や無生物になりきれる感受性だけが、真に自然を持続させるのです。