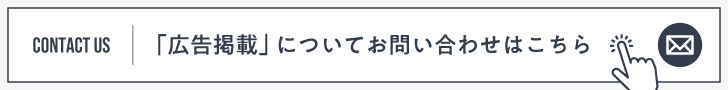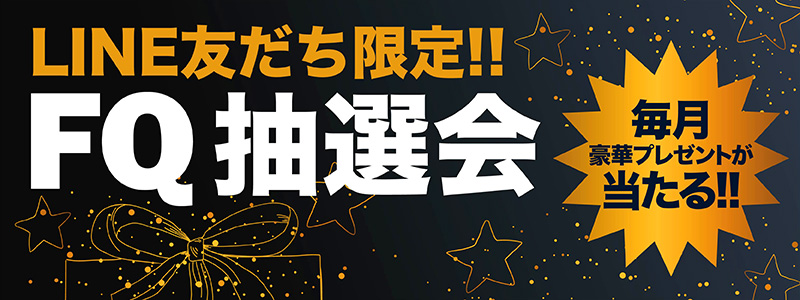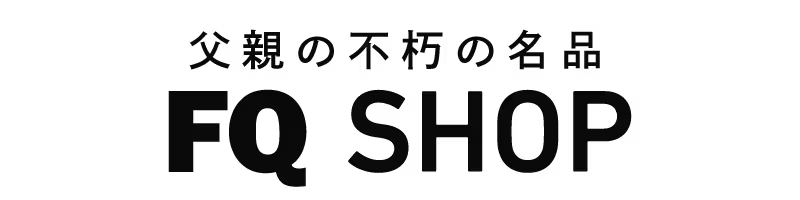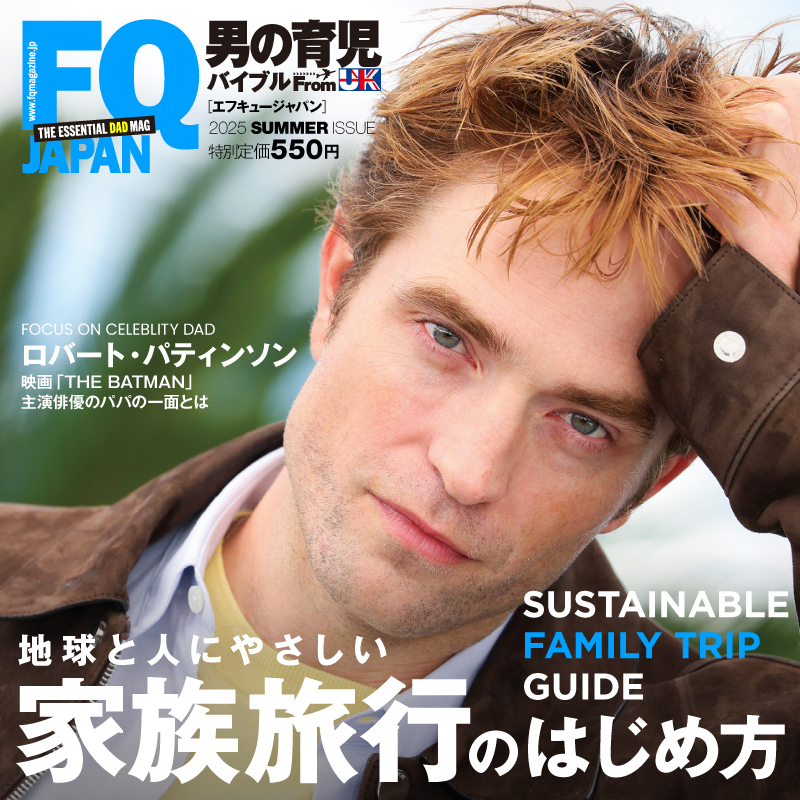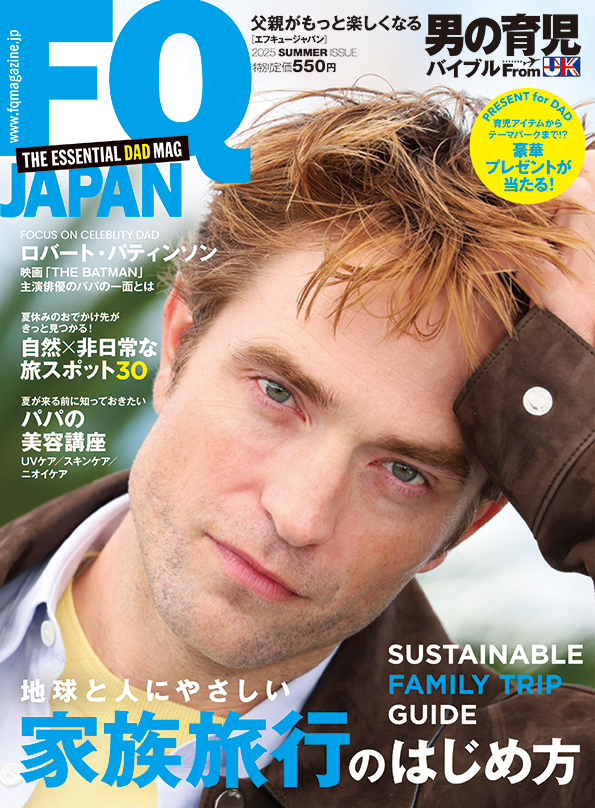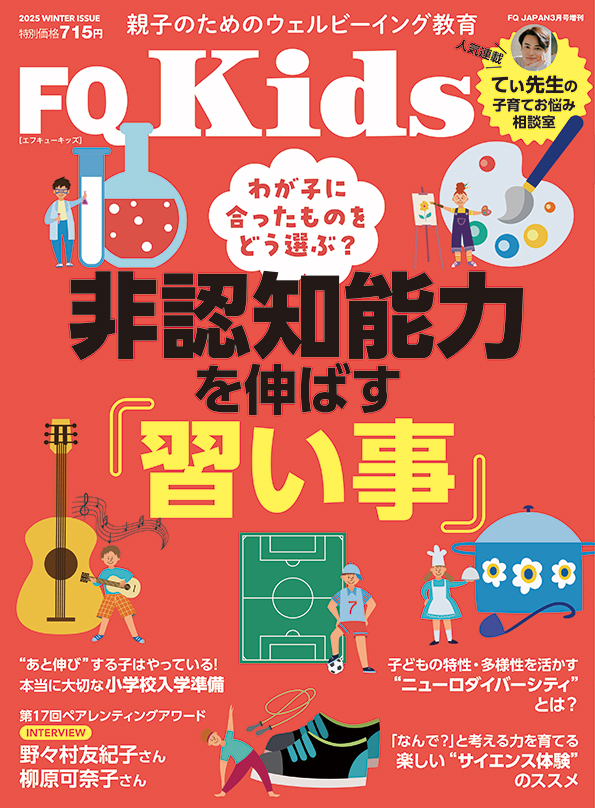産後のママはどんな状態? 妻を支えるために知っておくべき『産後ケアの基本』
2024/06/01

出産後は、赤ちゃんのケアだけに目がいきがち。でも出産という大仕事を終え、慣れない育児に奮闘する産後ママの負担は、心身ともに絶大だ。産後ママの心とカラダをサポートする“産後ケア”にはパパの協力が必須。出産前から正しい知識を身に着けて、心の準備をしておこう。
What is“ 産後ケア”?
産前から産後に変化する女性の心とカラダ。環境の変化も相まって、産後の女性には大きな負荷がかかるもの。
“産後ケア”とは、産後の大変な時期、心とカラダ、そして子育て環境も含めた産後の女性への包括的なケアのこと。ママ自身が心身ともに健康であることは、家族のみんなの幸せにもつながるのだ。
想像以上に全身がボロボロ……
産後ママのカラダを知ろう
出産は、まさに命をかけた大仕事。産後ママのカラダには、様々な傷や不調が生じている。なかでも最も大きいダメージを受けているのが、子宮だ。胎盤が剥がれたあとの子宮壁には、直径30cmほどの円形の損傷ができ、見た目にはわからなくても実際、大ケガを負っているのと同じ状態に。産後、ゆっくり寝て養生する必要があるのは、このためだ。
「産褥期」とは、妊娠前の状態にカラダが完全にもどるまでの産後6~8週間のことを指すが、回復には個人差があり、産褥期が終わってもなかなか体力が戻らない人も。赤ちゃんのお世話も大変な時期なので、パパを筆頭に周囲がしっかりサポートすることが大切なのだ。
産後ママのカラダ
骨盤 「出産で開ききった骨盤は、産後グラグラした状態。骨盤底筋群が伸びて断裂するなどのダメージを負うことで、尿もれがしばらく続くことも。
お尻 ホルモンの影響や腹筋が弱まることが原因で、産後ママは便秘になりがち。また、出産時のいきみや子宮の痛みにより、痔になることも。
乳房 授乳によって、乳首は傷だらけに。母乳の分泌が盛んになると、乳腺が張り、ズキズキとした痛みを感じるように。
お腹 出産したのにヘコまないお腹、妊娠線や黒ずみが残る皮膚など。外見の変化が産後ママにとって大きな悩みの1つになることも。
子宮 見た目にはわからなくても、出産によって大ケガ同然のダメージを負っている。出産後1ヶ月ほどは出血が続く。
肩 育児の緊張や、首の座らない赤ちゃんを抱っこする時の不自然な姿勢などによって極度の肩こりに。
肌 目元のクマや脇、乳首などの黒ずみ、肌の色が濃くなることも。
……他にも、髪の抜け毛、筋肉痛、眼精疲労、腱鞘炎、筋力低下などカラダのあちこちで不具合が!