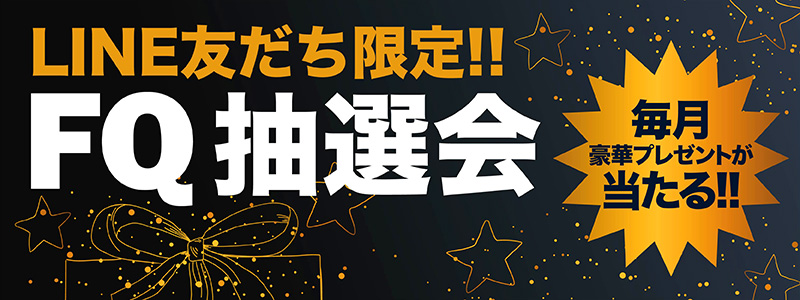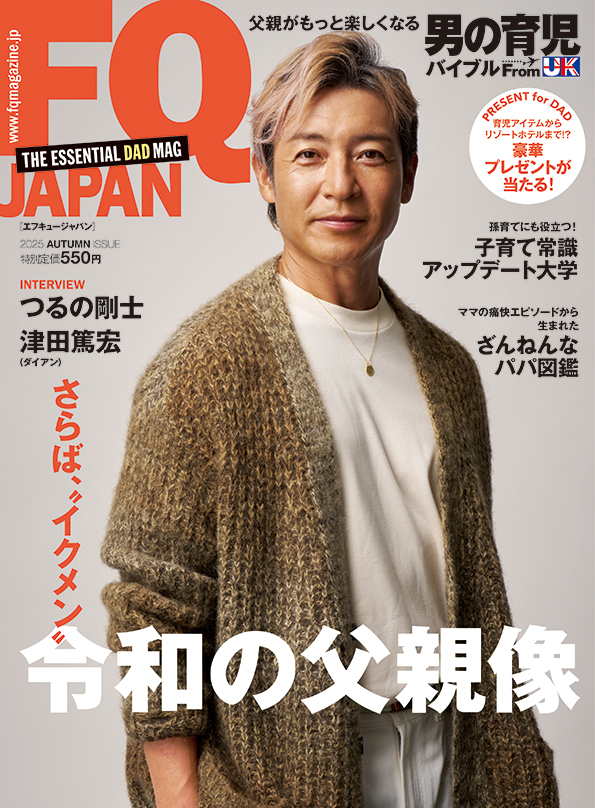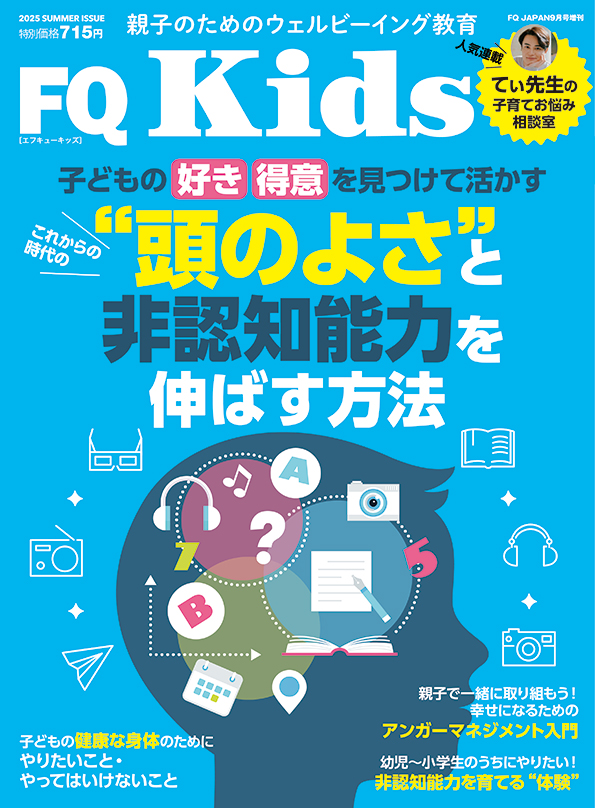情報社会を生き抜く必須能力!子どもの「判断力」を養う親子の会話とは
2024/12/19

「子どもを失敗から守りたい」という考えは、ごく自然な親ごころ。しかし、「すべてを親が決めてしまうと判断力を身につける機会を奪ってしまう可能性がある」と、心理カウンセラーの五百田 達成さんは警鐘を鳴らす。子どもの判断力を養う重要性を伺った。
判断力の養成に必要なのは
親子間のコミュニケーション
ー五百⽥さんは、「判断力の養成」にポイントを置いた子育てを推奨されています。なぜ、「判断力の養成」を重視しているのでしょう?
今の子どもは、私たちが子どもだった頃とは大きく違う環境で生きています。スマホやSNSがある現代は、見知らぬ人とコミュニケーションをとる機会や情報にあふれており、現代を生きる子どもたちは、情報を取捨選択したり、自ら判断すべき場面に多々直面しています。だからこそ、判断力を養う子育てが必要だと考えたわけです。
また、私自身の生い立ちも、子育てに対する考え方に影響を与えています。私の両親は共働きだったので、子どもの頃はよく留守番を任されました。つまり自宅に来客があれば、子どもの私が対応するわけです。そうした状況をふまえ、母からは常々「自分の判断で行動しなさい」と言われていました。「家に荷物をもってきた人に『ここにハンコを押して』と言われるがままに、ハンコを押すのはやめなさい。自分でハンコを押していいかどうか、判断してから押すようにしなさい」と言われ、背筋が伸びる思いがしたのをよく覚えています。また、両親からは「自立しなさい」とも頻繁に言われていました。
そうした家庭環境があったからでしょう。私は青年期を迎える前に、自分の頭で考えて判断する習慣を身につけました。進路選択など重大な決断をする際も、両親をはじめとする他者に頼らず、自分の意志で決めていました。
今から考えても、自らの意志で物事を決める習慣を早い段階で身につけられたことは、自分の人生においてはプラスだったと感じます。
ー子どもの判断力を養うために、家庭ではどのようなことができるでしょう?
まず大前提として、子どもを「意志をもった一人の人間」として捉える必要があります。そのうえで日頃のコミュニケーションのなかで、子どもの意志を引き出していくといいでしょう。例えば、子どもがいくつかの選択肢を前にして迷っている時は、「なぜ迷っているの?」「どれを選択してもメリットとデメリットがあるはずだよ。両方のメリットとデメリットを明確にして、比較してごらん」といった声かけをしてあげましょう。あるいは、子どもに双方のメリットとデメリットをプレゼンテーションさせたり、お互いの考えを伝え合うといいでしょう。親と子どもが対等に意見を交わし合うという作業は、子どもの意思を引き出し、判断力を養ううえで大きく役立ちます。
お箸の持ち方や自転車の乗り方が、繰り返しの練習をとおして身につくのと同じように、判断力も、繰り返しの練習によって身につきます。前述したとおり、判断力を身につけるうえではプレゼンテーションや意見の交換などが有効です。家庭でも、親が主導するかたちでこれらを行うのが望ましいと考えています。
知識や情報が
より良い判断の助けに
ー考えうる限りのメリットとデメリットを挙げても、どうしても選択できないという場合もあるかと思います。その場合の解決策はありますか?
選択できないという課題の背景には、知識や情報の不足があるはずです。知識や情報が十分になければ、自信をもって選択できないのは当然でしょう。なので、選択する前に徹底的に調べてみるのもオススメです。例えばですが、子どもがプロテニスプレイヤーを目指すか、あるいは大学に進学するべきか、と2つの進路を前にして悩んでいるとします。その場合は、まずはプロテニスプレイヤーを取り巻く状況や、プロになるための道筋などを調べるのです。現在、プロとして活躍している人の何割がテニスだけで生計を立てているのか、本格的な練習を始めてからプロになるまでに平均で何年かかるのか、プロになるまでにどれくらいの資金がかかるのか、といったことを具体的な数値も含めて調べてみる。具体的な情報を集めるほど、より良い選択ができる可能性が高まるはずです。
ーありがとうございました。最後に、FQ JAPANの読者に向けてメッセージをお願いいたします。
日常的にSNSに触れており、社会とつながっている現代の子どもたちは、すでに“社会デビュー”しているといえます。多様な人々とコンタクトを取れる環境にある子どもを守るためにも、意識的に子どもの判断力を養っていく必要があります。
また、判断力を養うことは、自立心や生きる力を養うことにもつながります。自分の頭で考えて自分なりの決断を下す習慣を身につけることで、子どもは責任をもって、自分の人生を生きられるようになるはず。また、自分の足でしっかりと立ち、生きていけるようにもなるでしょう。判断力を養ってあげることは、子どもへのプレゼントであり、親としての最低限の責務だと考えています。
CHECK!
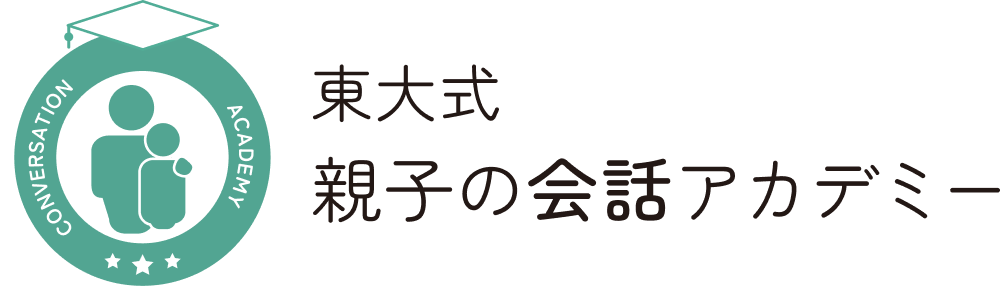
五百⽥さんが学長を務めるオンラインアカデミー「東⼤式親⼦の会話アカデミー」が、2024年10⽉1⽇に開校。当アカデミーでは、⼦どもの”判断する⼒”を育むための親⼦コミュニケーションを学ぶ「親のことば講座」、⾃分の⼦どもの特徴を知ることから始める「子どもを知る講座」、⼦どもの⾃⼰決定能⼒を⾼め、将来の⾃⽴につながるスキルを養成する「決めること習慣化講座」、場⾯に合った言葉を習得するためのトレーニング術を紹介する「⼦どものことば講座」の、4つのカリキュラムを用意。これらのカリキュラムをとおし、「自身で物事を判断できる子ども」の育成を目指す。
教えてくれた人
五百⽥ 達成(いおた たつなり)さん

作家・⼼理カウンセラー。東京⼤学教養学部卒業後、⾓川書店、博報堂を経て、五百⽥達成事務所を設⽴。「コミュニケーション×心理」を軸に、話し方・ことば・フェミニズムについて執筆・講演。著書に『超雑談⼒』『自分の気持ちを上手に伝える ことばの魔法図鑑』などがある。
文/緒方よしこ
編集協力/親子の会話アカデミー