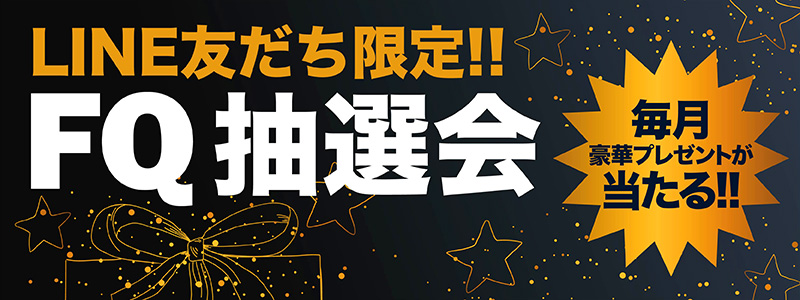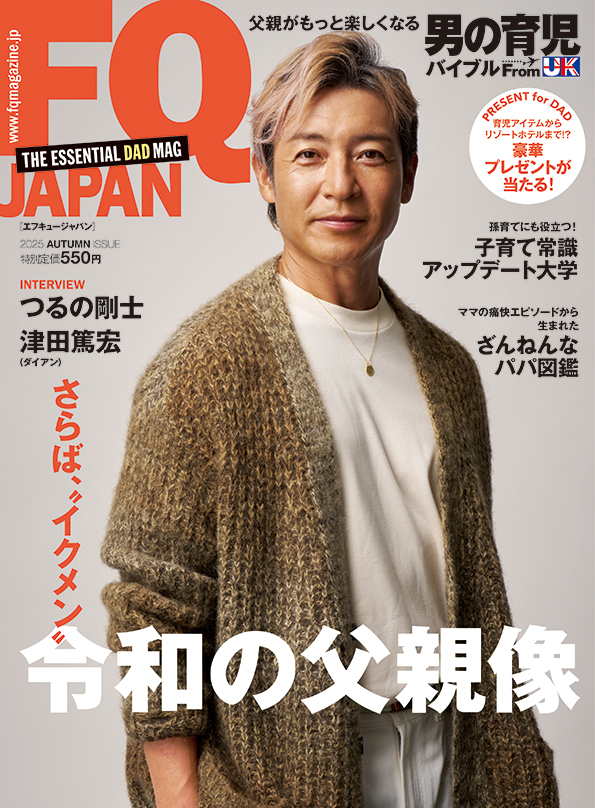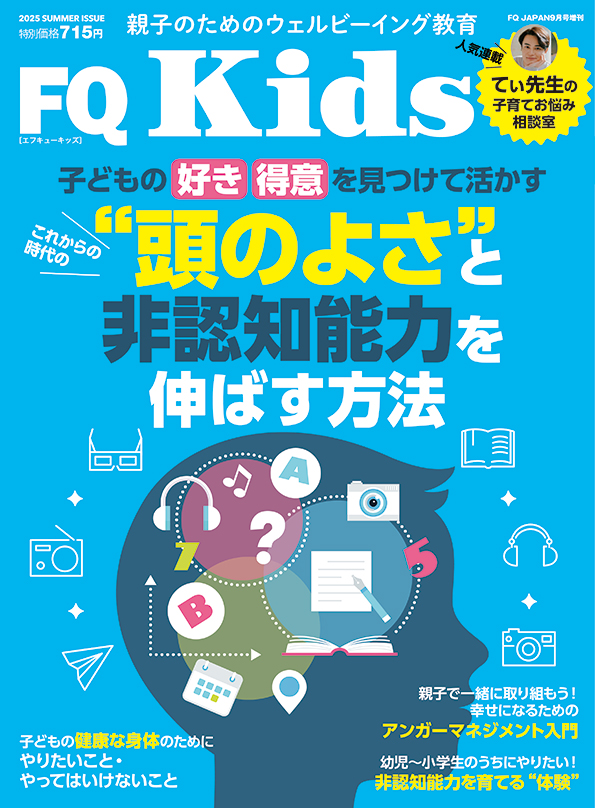「男性の育休」は子育てしやすい社会への変質のカギ
2016/08/09
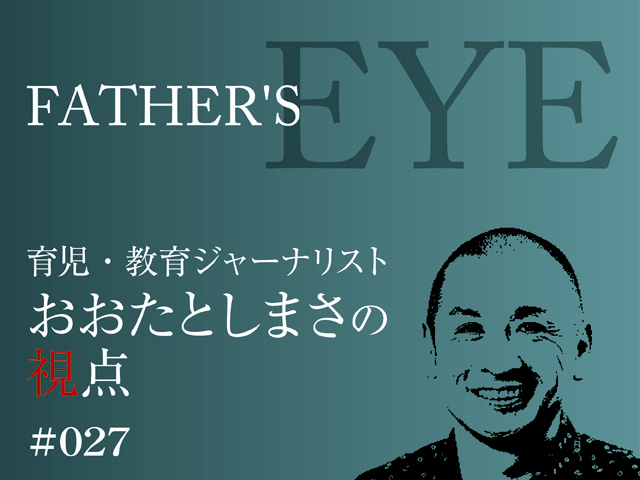
「教育ジャーナリスト・おおたとしまさの視点」連載第27回。ライフステージに合わせたライフスタイルとしての「育休」。
男性が育休を取る意義は何か?
<出産直後の育休>
● 出産直後、女性の心身へのダメージは大きい。産後の肥立ち。誰かがサポートしなければ赤ちゃんも母親も生きていけない。頼れる人がほかにいなければ必然的に夫のサポートが必要になる。
● 新生児とふれあい、世話をすることで、パパスイッチが入る。親としての自覚が芽生える。親としての自意識において、母親と差が開きすぎることを防ぐ。
● 早期に当事者として育児を経験することで、育児という営みに対するリスペクトを感じるようになる。父親がその後の育児生活において、補助的な役割を担うことになったとしても、母親に対するリスペクトを忘れない体質になる。
● 何よりも家族のことを大切に思い、それを実際に行動として表現してくれることで、妻は夫に対して安心感を抱くことができる。妻が安心していれば、子育ての安定にもつながる。
● 育休を取ったこと自体が、男性の父親としての自覚・自信を強化する。
● 育児体験のある男性が増えることで、職場での育児中の親に対する配慮が自然に行われやすくなる。それにより少しずつ社会も変質するはず。
※産後の肥立ちのサポートという意味では、退院後最低2週間。その間は24時間体制でのサポートが必要になる。しかしその後は無理に育休を続けなくても、定時退社を心がけるだけでも効果がある。
※いきなりはじめての家事・育児をしても不慣れで役に立たない。妊娠中から家事の訓練をしたり、両親教室で育児の予習をするなどしておいたほうがいい。
<妻の職場復帰に合わせての育休>
● 出産後8週間以内に男性が育休を取ると、もう一度育休を取る権利が生じる。これは妻が職場に復帰するタイミングでの育休を推奨する制度。
● 妻が職場に復帰するということは、子供も保育園デビューするということ。妻は久しぶりの職場で浦島太郎状態。子供も初めての保育園でストレスが多かったり、病気をもらってきたりする。朝、大泣きする子供を保育園に置いて職場に向かうのも大きなストレス。そのうえ子供が急に熱を出して呼び出しを受けることも多い。そこで父親が一定の役割を果たさないと、妻は職場復帰直後から仕事と育児の両立でてんてこ舞いになってしまう。せっかく職場復帰をしてもすぐに行き詰まり、結局退職するケースも多い。
※子供が熱を出して呼び出されることはしばらく続くので、できることなら保育園デビュー後数ヶ月、妻の仕事が軌道に乗るまでは、父親は、育休を取らないまでも、いざというときに自分が保育園のお迎えに行ったり、会社を休んだりできるように、仕事量を調整できると理想的。