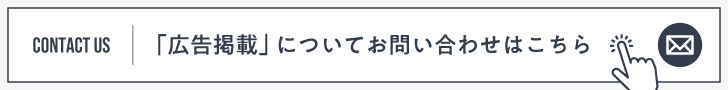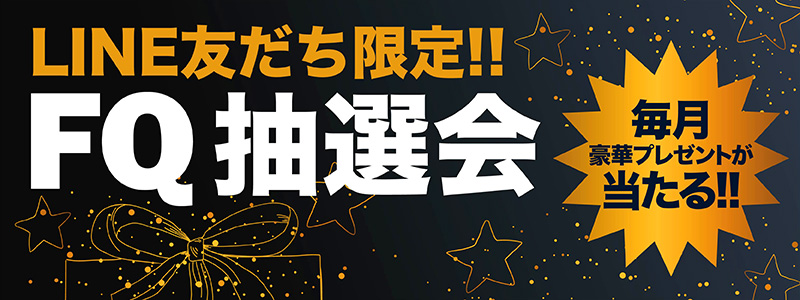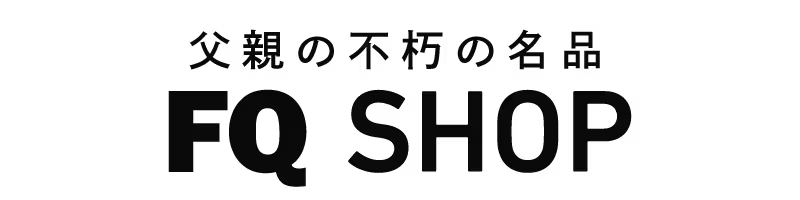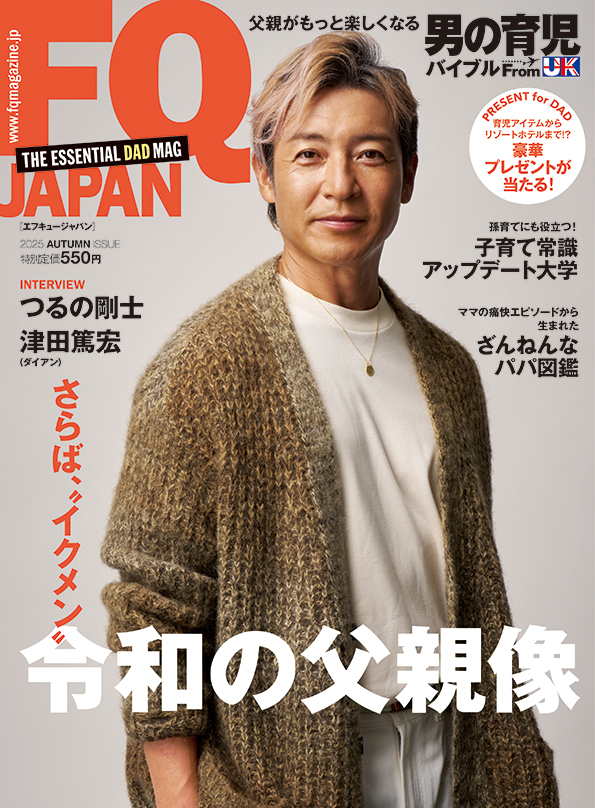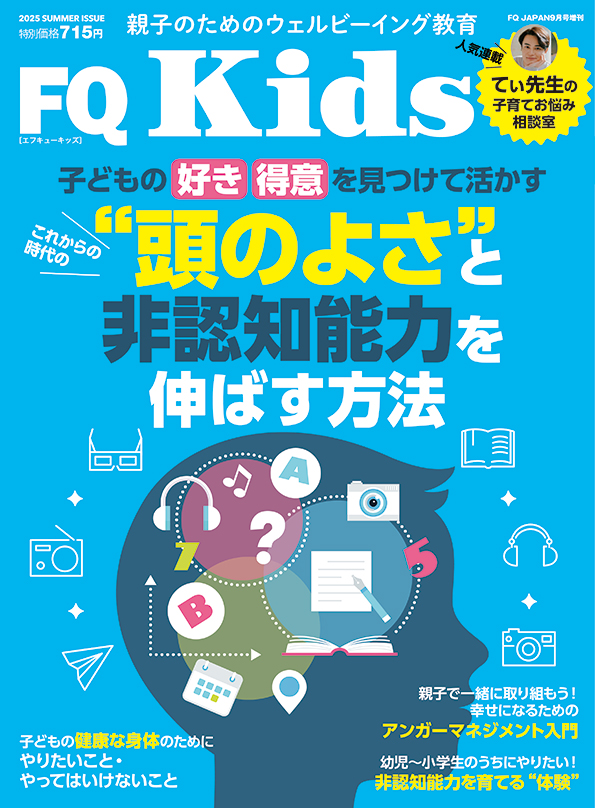【令和の子育て常識】スマホは「ワンポイントリリーフ」でOK!ゆる育児という選択
2025/11/06

昭和・平成の育児常識は、令和の今では通用しないことも。完璧を目指さない「ゆる育児」、親の健康を守る大切さ、デジタルとの付き合い方、母乳や離乳食の最新情報など、今の時代に合わせた子育ての新常識を解説する。
1. きっちり完璧育児より親の健康も何より大切
2. 完璧な育児を目指さない
3. スマホ・デジタル接触は「ワンポイント」で
4. それってわがまま?「育児神話」を情報更新
5. 母乳育児・粉ミルクの常識は変わった?
6. 離乳食のアレルギー対応が大幅改定
きっちり完璧育児より
親の健康も何より大切
育児はすべてをきっちりこなす必要はない。親が疲弊してしまえば、子どもの心身にも影響が及ぶ。令和の育児観では、親が元気でいることが子どもの健康を支える前提条件だ。
昭和・平成では「子どものためなら親は我慢」が美徳とされたが、今は違う。親自身が十分に休息を取り、心身の健康を維持することが、結果的に子どもの健やかな発達につながると考えられてきている。
育児はチーム戦であり、パートナーや祖父母、地域資源を活用しながら「困った時には助けを求める」ことが大切だ。
完璧な育児を
目指さない
育児は完璧にしすぎず、ゆるいくらいがちょうどよい。例えば、わが子の発達を気にして、成長曲線(子どもの身長や体重などの身体的な発達をグラフで表したもの)から外れていると心配になってしまうことがある。しかし、成長曲線や発達の指標はあくまで平均であり、発達には幅があることを理解しておくと安心だ。
とはいえ、全く気にしなくてよいわけではなく、小児科医から見てフォローが必要な場合もある。自分で情報を調べていると、不安な情報ほど頭に残りやすいもの。調べ過ぎて気に病む前に、気になるときには専門家(小児科医や自治体の相談先など)に早めに相談することがおすすめ。
スマホ・デジタル接触は
「ワンポイント」で
幼児のスマホやデジタルデバイスの使用は、近視や視力低下のリスクがあること、言葉の発達や認知機能の発達に影響が出る可能性が研究で示されている一方、単独で視聴するのではなく保護者と一緒に視聴したり教育的なコンテンツを利用したりすることはポジティブな効果をもたらすとの報告※もある。
大人がスマートフォンに依存している中で、子どもだけを禁止するのは難しい現実がある。バスや電車の中など、一時的なワンポイントリリーフとしてデジタルデバイスを利用することでうまく乗り切れることもある。
ゲーム依存も最近の課題だ。対処するのは早めが肝心で、小学校低学年までに家庭でルール作りをすることが重要だ。厚生労働省の保護者向けリーフレット「ネット・スマホのある時代の子育て(乳幼児編)」も参考にしよう。
※医学誌『JAMA Pediatrics』掲載論文「Early Childhood Screen Use Contexts and Cognitive and Psychosocial Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis」(早期幼児期のスクリーン利用の文脈と認知・心理社会的転帰:系統的レビューとメタアナリシス)
それってわがまま?
「育児神話」を情報更新
育児に関して昔は当然のように語られていたことが、今では真逆の認識になっていることもある。例えば、「抱っこは抱き癖がつくからしすぎない方がよい」という言説があったが、医学的根拠はない。現在は、泣いたときに抱いてあげることで自己肯定感や他人への信頼感が育つと考えられており、抱き癖は気にしなくてよいとされている。
また、広く語られていた「3歳児神話」(子どもが3 歳になるまでは母親が家庭で子育てをするべきという考え)も、1998年の厚生白書で「合理的な根拠は認められない」と公式に否定されている。「0歳児から保育園に入れたら子どもがかわいそう」と言う祖父母世代もいるかもしれないが、現在は、保護者が子どもと一緒にいる時間に適切な関わりができれば大丈夫という認識が主流だ。保育園で同世代の子どもと広く交流ができることは発達を促すメリットもある。
母乳育児・粉ミルクの
常識は変わった?

母乳育児が推奨されていることは、今も変わらない。母乳には赤ちゃんの免疫を高める物質が含まれていることや、SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクを下げる効果も指摘されている。ママの産後の身体回復を促すオキシトシンというホルモンの分泌を助けるメリットもある。
しかし、完全母乳育児ができない場合はミルクの授乳で栄養を補えば大丈夫。2019年以降は、液体ミルクが日本でも発売されるようになった。70度以上のお湯で殺菌する必要がないこと、調乳の手間がなくそのまま飲ませられることから、外出時や夜間に調乳が大変な時や、災害時や備蓄用に活用できる。なお、保存期間はメーカーにより異なるので注意しよう。
離乳食のアレルギー対応
が大幅改定

かつては、「離乳食を早く始めると食物アレルギーになりやすい」という通説があった。赤ちゃんの消化管は未発達なので、早く始めてしまうとアレルギーが出やすいと考えられていたのだ。
しかし、最近、多くの研究から、むしろ消化管から吸収されたものは食物アレルギーになりにくいということがわかってきた。現在は離乳食が始まったら、卵や乳製品、小麦といったアレルギーになりやすい食べ物を遅らせる必要はなく、離乳食の本などでお勧めされている通りに進めていけばよい。ただし、初めて食べるものは少量から始め、卵はしっかり火が通ったものから始めることが大切だ。
祖父母世代との
「子育て常識」ギャップ解消シート

出典:森戸やすみ「祖父母手帳」(日本文芸社)、教えて!ドクター「子育ての今」
教えてくれた人
坂本昌彦先生

佐久総合病院佐久医療センター小児科医長兼国際保健医療科医長。小児救急を専門に国内外で臨床経験を積み、「教えて!ドクター」プロジェクト責任者として保護者啓発や救急外来負担軽減に尽力。Eテレ「キッチン戦隊クックルン」などの医事監修などを担当。
教えてドクター!
公式サイト・アプリ

「教えて!ドクター」は、長野県佐久地域の小児科医が作成した、子育て中の親の不安をケアするためのwebサイトとアプリ。アプリは子どもの症状から受診の目安を調べられる機能をメインコンテンツとして提供していて、親が不安なときに適切な判断ができる。予防接種スケジューラー機能も搭載されており、計画的な予防接種の管理ができる。自治体(長野県佐久市)が支援しており、無料で広告もないため使いやすい。

取材・文:東 麻吏
FQ JAPAN VOL.76(2025年秋号)より転載